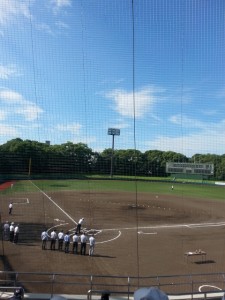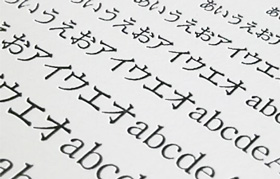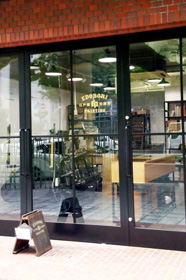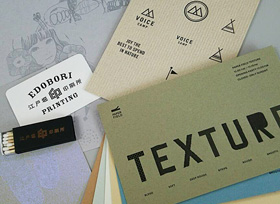こんにちは。
事の発端は前回のアナ雪なのですが、どうしてもディズニーに行きたくなり、
東京に結婚式に行く妹にひっついて、私も行ってきました!
(参照:アナと雪の女王を観にいきました)

1日目はディズニーに2人で行き、ミッキーとハグしてご満悦。
連日夏日が続いてましたが、この日は、あいにく雨&曇り!
大変すごしやすかったです(笑

2日目は妹は結婚式のため、私は一人で東京観光でした。
さて、東京観光何しよう。。。と考えて、
1度テレビで見てすごく気になっていた、前川國男邸をみに行くことにしました。
前川國男邸は最初、品川区に建てられましたが、現在は『江戸東京たてもの園』という、
野外博物館の中に移築されています。
何がすごいとかは、全然知らないんですけど、すごく好きなんですよね~。
将来こんな家建てたいです。
江戸東京たてもの園には、ほかにも江戸時代から昭和初期までの、復元建造物が建ち並んでいます。
全体的に大きな公園になっていて、大変すごしやすい場所でした。
行くのには少し苦労しますが。。
もし機会があれば、みなさんも是非。
開発のなかまるでした。

追伸:
写真を見た母親に、『結婚もしてないくせに、子宝湯なんて行ってどうすんのよ!』と言われました(笑